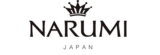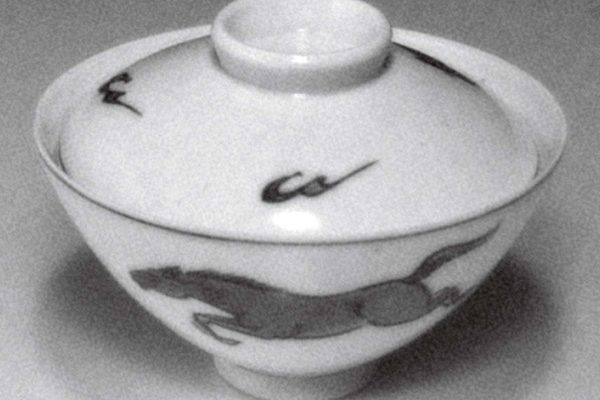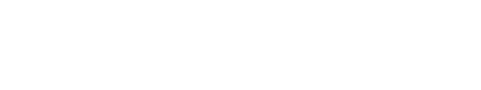ホーム » フィロソフィー
NARUMIの歴史
日本の歴史に「なるみ」の名が現れたのは、日本武尊が東征の折に詠んだ歌の中です。鎌倉時代には京都鎌倉を繋ぐ街道の要地として、その後 東海道五十三次 四十番目の宿場町として栄えました。江戸時代初期には、鳴海の里においても鳴海焼が焼かれた歴史があり、幕末のころにも焼き物を焼く窯の煙が上がっていたといいます。
その鳴海の地に、1938年 名古屋製陶株式会社が、ドイツ式陶磁器の新工場を建設し、陶磁器の生産を始めました。しかし、開戦により住友金属工業株式会社が、国からの要請を受けて航空機の部品を製造するために、その工場を買い受けたのは1943年のことです。これにより製陶設備は次々に撤去されていきました。
1946年
創業
終戦後のまだ瓦礫の残焼け野原の中、製陶設備がほとんど残っていなかった工場に僅かに残った茶碗やカップ。それを見て、「いつの時代にも変わらずにある食卓の幸せ」を願い、日本が失いかけた「家族の団欒」「上質で幸せな時間」を取り戻すことを夢見て、残されたわずかな設備と技術者、そして全従業員が一丸となって窯業にゆかりのある鳴海という地に「鳴海製陶所」として新たに創業させました。
しかし、まだ十分な原料も手に入らない時代。最初の試験窯から出てきた飯茶碗は、お世辞にも“白い磁器”とは言えないものでした。しかしその経験はのちに、より白く、良質な磁器を皆さまに届けたいという、強い想いとなりました。当時の競合他社が、タイルや衛生陶器といった比較的工業規格化しやすい分野に舵を切る中、あえて技術レベルが高く、難しい洋食器のディナーウェアに挑んだのは「いいものを作り続ければ、いつかそれを豊かに活かす、幸せな時代が訪れる。」という信念の上での行動でした。
1965年
ボーンチャイナ製食器のアメリカ向け輸出を開始・原料に関する特許取得
海外市場で、NARUMIの陶磁器は、そのシェイプデザインと絵柄の美しさで人気を博しますが、どうしても超えなければならない壁がありました。それは、高級磁器“ボーンチャイナ”でした。
「ボーンチャイナに手を出すと、会社はつぶれる」とまでいわれていた当時、NARUMIは非常に困難とされた量産化に挑戦し、日本で初めてボーンチャイナ製ディナーセットをアメリカに出荷するという偉業を達成しました。陶磁器に比べて素材の扱いが難しく、一部の限られたメーカーでしか製造されていなかったボーンチャイナの量産化に成功するということは大変な苦労の連続でした。この時、原料に関する特許を取得し、ボーンチャイナ生産のリーディングカンパニーとしての立場を確立しました。美しく作り上げられたディナーセットの販売は、私たちが夢見てきた「上質で幸せな時間」の象徴であり、永年の願いが実を結んだ瞬間でした。
1982年
三重ナルミ株式会社設立
この頃、消費者の高級志向が一段と進み、海外のみならず国内におけるボーンチャイナの需要が大きく伸びていきました。品質を保ちつつ安定した生産体制を整えるため、国内にボーンチャイナの一貫工場として新しく建設しました。当時における国内最大級の生産規模と、技術育成を行うことで得た新たな装飾技法は、後にスーパーボーンチャイナ「クロン・ド・ミューズ」と呼ばれる高度な加飾技術を用いた最高級ボーンチャイナの開発につながっていきました。
1991年
初の海外子会社設立
シンガポールに初の海外販売子会社を設立、同時に香港に駐在員事務所も設立しました。創業より大切にしている良質なディナーウェアへのこだわりは、「より高い品質の陶磁器を世界の市場に送り出したい」という想いへとつながっていきました。グローバルな視点から食・文化について考え、「いつの時代にも変わらずにある食卓の幸せ」を世界の市場でも叶えようとビジネスの場を広げていきました。
特殊絵具開発の成功
一方、NARUMIのもう一つの柱である産業器材事業は、超耐熱結晶化ガラス製トッププレートへの装飾の一つとして特殊絵具「ラスターペースト」の材料開発を成功させました。食器の装飾技法から発展したこの材料はガラス業界では一般的に行われることのない透明板の裏面に黒く着色することを可能にし、ガラス加工製品の幅を大きく広げ、新しい商品開発へとつながっていきました。
1995年
インドネシアに海外生産拠点設立
海外生産拠点としてPT NARUMI INDONESIAを設立いたしました。日本人技術スタッフが駐在し、MADE in JAPANと同じ品質を保ちながらより多くの製造が可能になりました。拡大する海外市場や流通経路への迅速な対応を実現し、アジアを中心に世界中に日本の技術を提供する拠点となりました。
2005年
中国に販売子会社設立
2005年、中国の法律が変わり外資100%で会社を設立できるようになったチャンスを利用し他社に先駆けて中国に子会社を設立。新制度の下で設立された外資系企業最初の200社に入っています。「いつの時代にも変わらずにある食卓の幸せ」への願いがアジア最大の市場に届きました。
2016年
アメリカに販売子会社設立
アジア圏以外で初の拠点となるアメリカに販売会社を設立しました。拠点を構えることで幸せをお届けしたいという想いをみなさまに直接お伝えできるようになりました。この想いは、日本からアジア、そして世界に広がりNARUMI の挑戦は続いています。